お客さんから一番良く受ける質問「樹木医ってどうやったらなれるんですか?」に答えます。
私も樹木医資格を取得してから十年弱が経過しました。
一部制度が変更になった点もあるので、2024年12月現在の情報をアップデートして解説します。
樹木医とは
一般社団法人日本緑化センターが認定する資格です。
樹木の生理・生態を理解し、調査、設計監理、維持管理業務に精通し、診断及び治療を行う専門家です。
いわゆる樹木のプロフェッショナル。
植物生理学や生態学に疎く科学的根拠に基づかない造園業者や土木業者が天然記念物の樹木を治療して枯らしてしまったなど、さまざまな社会背景があったことからこの資格ができました。
かつで発足当初(1~9期くらいまで)は、農林水産大臣が認定する資格でしたが、法律に基づかない資格に関しては民間主導で運営管理するとの方針が出たため現在では、一般社団法人日本緑化センターの認定となっています。
樹木医になる方法
樹木医になる方法は、以下の2つの方法で実務経験を積んでから樹木医選抜試験に合格後、樹木医研修を受ける必要があります。
1.樹木医補として登録後に樹木医になる
樹木医補資格養成機関として登録を受けた大学の農学部や生物資源学部などで所定の単位を取得し、樹木医補として登後、1年間実務を積んでから樹木医選抜試験を受験する方法です。
樹木医補の資格を取得するためには、以下の通りの条件があります。
講義科目6分野以上14単位以上の履修があり、かつ実験・実習科目4分野4科目以上の履修があること
これが結構大変ですが、樹木医研修よりもより広い範囲で専門的なことを学ぶことができます。
樹木医補が取得できる大学
樹木医補が取得出来る大学は、以下のとおりです。
現在、44の大学(短期大学を含む)と、19の専門学校(専門学校・専修学校等、農林大学校等を含む)が登録されています。
認定大学等一覧
https://www.jpgreen.or.jp/jyumokuiho/02_daigaku.html
2.実務経験5年を積む
樹木医補の資格を取得できないかたは、5年間の実務経験が必要です。
昔は、7年間必要でしたが、5年に短縮されました。
実務経験の内容については、以下の項目をご確認ください。
実務経験の積み方
実務経験となる業務内容は、樹木の調査・研究、診断・治療、保護・育成・管理、公園緑地の計画・設計・設計監理、緑化樹木や果樹の生産等に関する実務あるいは研究です。
日本緑化センターHPのQ&Aがよく書かれていますので、ご確認ください。
日本緑化センター よくある質問
https://www.jpgreen.or.jp/treedoctor/qanda/01shikaku.html#q1_2
自分の業務が実務経験になるかどうか判断ができない場合には、日本緑化センターに直接メールや電話で問い合わせるのも良いです。
丁寧に質問をすれば、きっと親切に答えていただけます。
ただし、緑化センターの人も通常業務がありますので、なるべく時間をとらないように簡潔に質問しましょう。
業務経験事例が大切
受験する際に提出する業務経験事例という書類があります。
これは、今まで自分がどのような業務に携わってきたかをアピールするシートです。
選抜試験合格後に実施する最終面接試験にも繋がることなので力を入れて書くことをオススメします。
なるべく自分がやった業務について詳細に記述するようにして下さい。
樹木医選抜試験
樹木医研修を受けるために樹木医選抜試験に合格する必要があります。
申込期間と試験日
申し込み期間は、例年5月から6月中旬です。
試験日は、例年7月中旬です。
選抜試験の試験内容
試験の内容については、以下のとおりです。
| 試験方式 | 出題数 | |
| 択一式(マークシート) | 35問 | 5択の中から1つ選ぶ |
| 論述式 | 3題 300字 | 問われた内容について論述 |
樹木医選抜試験の対策と過去問
樹木医選抜試験の対策方法についてご説明します。
大体、以下のことを守って勉強すれば受かると思います。
過去問の手に入れ方
受験にあたり過去問は必ず必要です。
樹木医選抜試験の過去問は、amazonとかでは取り扱いがなく日本樹木医会のオンラインストアのみで販売しています。
選択問題の5択については、マークシートです。
毎年、何題かは同じ問題が出ますので、選択問題は繰り返し勉強し完璧の状態にしましょう。
一般社団法人日本樹木医会
https://jumokui.jp/book-store
基本書は、樹木医の手引き
基本書として使用されているのが、樹木医の手引きです。
Amazonでも販売されています。
これが電話帳なみに厚く内容が濃いです。
基本的にこの手引きから出題されますが、内容が多すぎるため過去問をとけるようにするために出題箇所や間違った箇所を優先的に読み込みましょう。
決して頭から全部読み込むことはオススメしません。
論述試験対策は、グリーン・エージ
樹木医選抜試験には、300字 3題の論述試験が出題されます。
主に樹木医の手引きの内容を理解しているかについて問われます。
また、人に説明する能力やカルテを書く能力など文章力も同時に問われています。
日本緑化センターが発行する雑誌「グリーン・エージ」に過去の論述問題の模範解答が掲載されています。
こちらもチェックすることをおすすめします。
グリーン・エージ
https://jpgreen.shop/shopbrand/ga
大体3月号に掲載されています。
樹木医の年収
樹木医の年収としては、働き方や就職先によって様々ですが、多くの樹木医が以下の働き方をしています。
フリーの樹木医として活動する
行政や個人邸からの診断依頼を受けます。
費用については、前に記載した記事を読んでみていただけると助かります。
樹木医専業として業務を実施している人もいますが、剪定などの造園作業も並行して仕事にしている人も多いです。
また、最近では、樹木医が解説するツアーなども人気です。
年収については、完全実力次第ですね。
造園業者として働く
樹木医として診断や樹勢回復ができる造園業者として働く方もいます。
雇われだと年収は、300万円~500万円程度ですが、独立して経営者になれば1000万円以上も目指せます。
研究機関で働く
大学等の研究機関で働く樹木医もいます。
大学の給与と同等ですが、教授になれば1000万円以上の年収をめざせます。
公務員として働く
国、市区町村や都道府県の道路課、林務課などで働く樹木医の方もいます。
一般的な公務員の年収と同額の平均650万円程度です。
樹木医の難易度
この説明が難しい。
樹木医補から樹木医になる受験者は、大学で一通りの内容について学んでいるので、復習のために過去問を解けば合格します。
樹木医補を持っていない方は、過去問を中心に勉強して細かい内容については、樹木医の手引きを読み込むとよいでしょう。
参考図書なども日本緑化センターのHP上に出ていますが、まずは樹木医の手引きを優先してください。
登録更新制度
よく聞かれることが多くなった登録更新制度について説明します。
2020年あたりから樹木医の登録更新制度が、導入されました。
これにより、研修などで貯められる樹木医CPDポイントを5年間で100単位以上を取得して更新する義務ができました。
しかしながら、更新しなくても樹木医資格は剥奪されません。
もう一度いいます。
更新しなくても樹木医資格は、剥奪されません。
更新しなかった場合のデメリットというと、行政に配布される樹木医名簿の樹木医失効者欄というところに名前が掲載されます。
行政の入札の際に仕様書の中に“樹木医失効者でないもの”という条件がなければ、とくに問題ないです。
また、一度失効させると再取得しなければならない運転免許とは異なり、樹木医資格の場合には、樹木医CPDのポイントを100単位取得すれば更新できます。
更新制度になったから、もういいやとは思わないで是非試験にチャレンジしてみてください!
まとめ
樹木医制度が出来て約30年程度が経過して、全国3000人以上が認定されました。
試験合格後に1週間の泊まり込みの研修(自分のときは、2週間でした)をする資格は稀だと思います。
また、当時一緒に研修を受けた同期は今でもつながりがあり情報交換をしています。
我々のお仲間が増えることを祈っています。



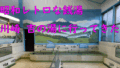

コメント