いつも立ち寄る蒲田駅のくまざわ書店の新書コーナーで気になる本を見つけた。
自分の文章に自身がなく、仕事で各メールも最近では、chatGPTに頼りっぱなしだ。
三十路も超えてこの文章力は、我ながら悲しくなってきたのと、いつもお世話になっている星海社の売上に少しでも貢献できればと思い一冊購入した次第だ。
いい本だと思ったので、共有させていただこう。
著者 古賀 史健 氏について
1973年生まれ。元々映画監督志望だったが、24歳でフリーのライターとなる。
シリーズ累計500万部の売上実績がある「嫌われる勇気」(ダイヤモンド社)などのヒット作を多く手掛ける。
嫌われる勇気は、書店でよく見る本だ。青い画用紙調の表紙を付けて商業的にヒットした本。
自分は、読んだこと無いがアドラー心理学について書かれているとのこと。
人間関係に悩みを抱える日本人にヒットするわけだ。
その気持ちを翻訳しよう
この章は、チュートリアルという位置づけである。
私のような文章を書くのが苦手な人間は、どのように書いたらいいのかがわからない。書きたい内容が頭の中には、あるのだが、うまく文章化することができず、筆が乗らないなどの悩みがあるものだ。
筆者は、この文章化できない気持ちを「頭の中のぐるぐる」と定義しており、この「頭の中のぐるぐる」を翻訳することが、文章を書くということと述べている。
非常に納得するし、共感できる。
僕は、書店でこの本を手にとって、立ち読みをした際に、この章に思わず共感をしてしまい。
購入を決意した。
文章は、「リズム」で決まる
「美文より正文をめざすべきである」
第2章にあたるこの章は、句読点や文節の区切り方などのテクニック的なことに加えて、文章内容の整合性についても述べられている。
いわゆる文体と呼ばれるものだ。
この本の中で読者は、文体とは、語尾である“です・ます調”や一人称主語“ぼく、わたし”などではなく、論理展開の整合性がとれている文章こそが、良いリズムのとれた文章なのだと説いている。
非常に納得だ。
昨今のyoutuberやネットニュースに記事には、論理展開に整合性の取れていない記事が溢れている。
こういう文章を読んでいくうちに自分でも気づかないうちに毒されてしまっているのかと思うとゾッとする。こういう文章に毒されないようにするためには、古典やまともな新書などを読んで自分をチューニングする必要があるかと思う。
また、以前に自分は、上司に「君の文章は、リズムが悪い」と指導されたことがある。
その上司曰く、長い文章と短い文章を交互に執筆しろとのこと。
これは、自分のような文章下手でも誤りだと気づくが、いかんせん周りがイエスマンで固められた人間なので、60で定年を迎えても自分が必ず正しいような物言いで読みにくい文章を生産し続けている。
僕は、この本に出会えて幸運である。
構成は、目で考える
著者の古賀氏は、若い頃には映画監督志望だったらしい。
そのため、ある程度の長文を書く際には、映画の絵コンテの容量で書き方を説明している。
これが非常にわかりやすい。自分なりに取りまとめたものを記すが、ぜひ読んでもらいたい。
- 導入(序論)=客観のカメラ
小説でも論説でも文章を読んでもらうために、読者を引き込む機能を持つ。客観のカメラとされているのは、読者に概略、状況について知ってもらうため。 - 本編(本論)=主観のカメラ
ここは、導入に対して自分なりの意見を展開する。自分の意見を主張するので当然、主観のカメラとなる。 - 結末(結末)=客観のカメラ
結論が客観のカメラとなるのは、本論の意見を客観的理由で補強するため。ただの主張ではなく「証拠があってこのようなことになってますよ!」と述べる
リスト化して話してみたが、読み返してみると著者の具体例があって腹落ちする内容。ぜひとも本書をよんでもらいたいです。
原稿にハサミを入れる
簡単に説明すると映画の編集と同じで推敲して内容に上澄みを読者に届けよう。
非常にもったいない気持ちになるのだが、どんなたくさん書いたとしても大事な部分のみ読者に届けるべきであると述べている。
著者が努力してたくさんの文章を執筆したとしても読者が途中で飽きてしまったらそれまでなのだ。
読者が読みやすい形まで推敲しようとのこと。
まとめ
まぁ、いろいろ述べてきましたが、テクニック的なことだけでなく本質を述べていると思う。
また新書なので2,3時間で読める割には内容が濃い。
僕もそうしたように、是非手にとって読んでもらいたい。

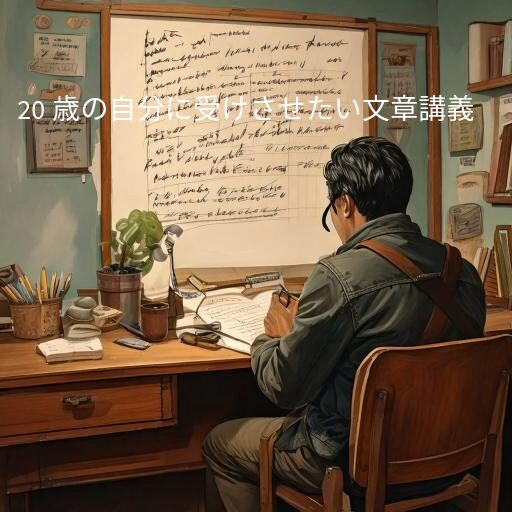


コメント